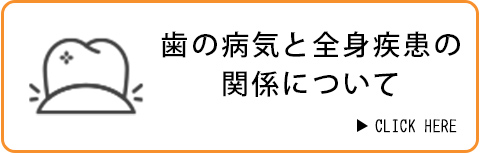- TOP >
- お口と身体の関係
お口の病気はむし歯や歯周病だけではありません
糖尿病と歯周病の関連
糖尿病と歯周病は互いに影響し合う危険因子であることがわかっています。糖尿病の患者様が歯周病になると、歯茎の血管が傷つきやすくなったり、歯周組織の新陳代謝の悪化、免疫機能の低下、唾液が減少して口が乾燥しやすくなることがあります。
重度の歯周病は、糖尿病患者様において心臓病や腎臓病のリスクを高めることもあります。
逆に、糖尿病患者様が歯周病の治療や管理を受けることで、血糖値のコントロールが改善されることも報告されています。このように、糖尿病と歯周病は非常に密接な関係にあることが明らかになっています。
当院は、地域のかかりつけ医院との連携を深め、患者様に対する医療サービスを総合的に向上させることを目指しております。糖尿病や歯周病にかかっている患者様に対して、糖尿病の専門医を紹介するなどの連携を行い、予防や治療に努めてまいります。
誤嚥(ごえん)性肺炎
誤嚥とは、摂取した食べ物をうまく食道に飲み込めず、気道のほうに飲み込んでしまうことです。気道に異物が入ると、通常は反射機能がはたらいて、むせて気管から異物を排出します。しかし、反射機能が衰えて誤嚥を起こしてしまうと、気管や肺炎に炎症を起こす引き金になります。誤嚥性肺炎とは、誤嚥によって起こる肺炎です。
お口の中が不衛生でむし歯や歯周病の原因菌が多いうえに、抵抗力が弱くなっていて、誤嚥を起こしやすい状態では、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。とくに高齢者の場合には重篤な状態を招く危険性があるので注意が必要です。
誤嚥性肺炎の典型的なサイン
とくにご高齢の方に次のような症状がある場合には、誤嚥性肺炎かもしれませんので医療機関にご相談ください。
- 発熱
- 激しい咳(せき)と色の濃い痰(たん)
- 荒い呼吸
- 肺雑音
気をつけたい日常の症状
ご高齢の方の次のような変化には、さまざまな原因が考えられます。肺炎もその中の一つですので、注意してください。
- 元気がなくなってきた
- 食事時間が長くなってきた
- 食後、ぐったりと疲れている
- ボーっとしている時間が長くなった
- 失禁するようになった
- 口の中の食べ物をなかなか飲み込まない
- 体重が減ってきた
- 夜間に咳き込む
ドライマウス
ドライマウスとは、唾液の分泌量が少なくなり、お口の中が乾燥することです。唾液は、耳下腺(じかせん)、顎下腺(がっかせん)、舌下腺(ぜっかせん)の3つの大唾液腺と舌や上顎にある多数の小唾液腺から分泌されます。健康な成人が分泌するのは1日になんと1~1.5リットルです。何らかの原因で唾液の分泌量が少なくなるとさまざまな症状があらわれます。
ドライマウスチェック
次のような症状がある場合にはドライマウスかもしれません。気になる方はお気軽にご相談ください。
- 口の中が渇く
- パンやビスケットなど乾いた食品が食べにくい
- 口の中がパサパサ、ネバネバする
- 味覚の好みが変わった
- 味を感じにくい
- 口の中がヒリヒリする
- 入れ歯が痛い
- 口臭が強くなってきた
唾液分泌が低下する理由とおよぼす影響
唾液が減ってしまう理由はさまざまです。一般的に夜になると唾液の分泌量は低下しますので、口腔内の細菌が増殖します。すると口臭やむし歯、歯周病のリスクが高まりますので、就寝前と朝起きたときの口腔ケアが大切です。
そのほか、唾液が減少する原因として、ストレスや不規則な生活習慣、お口まわりの筋力低下などがあり、薬の副作用や糖尿病などの病気との関連も原因として疑われます。また、加齢や口呼吸、喫煙習慣も唾液減少の引き金になります。
また、唾液にはお口の自浄作用があるので、唾液が減ってしまうと、むし歯や歯周病、口臭や口内炎などのトラブルに見舞われる心配もあります。そのほか、入れ歯が当たる部分が痛むこともあります。さらに食べ物を飲み込みにくくなり、誤嚥性肺炎を引き起こすこともあります。
唾液の8つの役割
唾液の99%は水分ですが、残りの1%には免疫や抗菌作用、そして消化などに関わる重要な成分が含まれます。唾液はお口の中を潤すだけでなく、さまざまな作用でお口のトラブルを予防しているのです。ここでは唾液の役割を8つご紹介します。
- 自浄作用:お口の中の食べカスや歯垢(プラーク)を洗い流します
- 抗菌作用:お口の中の細菌の増殖を抑えます
- pH緩衝作用:飲食により酸性に傾いた口腔内を中和させます
- 再石灰化作用:脱灰して溶け出した歯の表面の成分をふたたび歯の表面に定着させる再石灰化を促します
- 消化作用:酵素アミラーゼがでんぷんを分解し消化を助けます
- 粘膜保護・潤滑作用:粘性のあるムチンが粘膜を保護し、発声をスムーズにします
- 溶解・凝集作用:咬み砕いたり、味を感じさせたり、飲み込んだりしやすくします
- 粘膜修復作用:上皮成長因子と神経成長因子が粘膜の傷を治します
唾液の分泌を促進させる4つの方法
- よく咬んで食べる
- しゃべる、歌うなどで口のまわりの筋肉を動かす
- 口の中を清潔にする
- 唾液腺マッサージを行う
気になる症状がある方は、お気軽に当院にご相談ください。